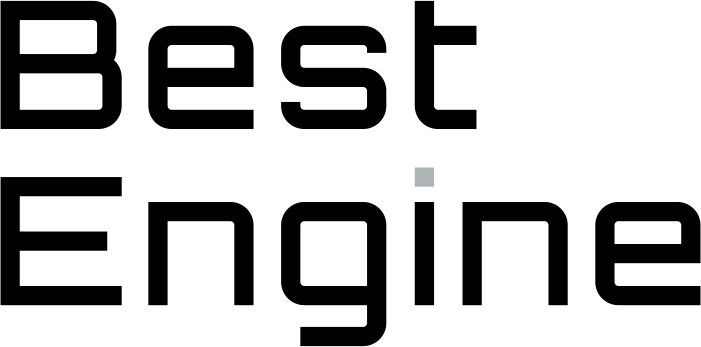ゴルフダイジェスト編集 世界のゴルファーを魅了する名門コースの流儀
「パインバレー」が世界No.1と言われるその理由とは?
パインバレーゴルフクラブ
ゴルフコースのワールドランキングが誕生して以来、長年にわたり首位に君臨し続けるパインバレーゴルフクラブ。
そこには名門と言うにふさわしいコース、そして、伝統が息づいている。

川田 太三
日本ゴルフコース設計者協会 理事長
株式会社ティアンドケイ 代表取締役社長
1944年、東京都生まれ。
米国オハイオ州立大学を経て1967年、立教大学法学部卒業。ゴルフ場の設計23コース、改造29コースのキャリアを持ち、全英、全米などメジャートーナメントのレフェリーも歴任。
パインバレーゴルフクラブ(以下、パインバレーGC)といえば、コースの価値に、「世界一」の称号が必ず付いて回ります。1970年代の後半から米国の2大ゴルフ雑誌(『ゴルフダイジェスト』『ゴルフマガジン』)が、「アメリカのベスト100コース」と銘打った企画を始めました。ゴルフ界の有識者を集めてパネルを作り、2年ごとに(両誌隔年)このリストを公開したのです。パネラーはレイアウト、戦略性、デザインバランス、各ホールの記憶度、ロケーションの美しさ、メンテナンス、伝統などの要素を加味して、点数を付けて発表しました。
1913年、米国のニュージャージー州パインバレーに開場したパインバレーGC。最初の数回は“最も難しいコース”のリストアップでしたが、その回も含め、何度かの例外を除いて、同GCはずっと首位の座を維持し続けています。
なぜそれほどまでに高い評価が続くのか、私なりに分析していきたいと思いますが、その前に私と同GCの関わり合いを話しておきましょう。
バンカーの数は無数 荒地型、可罰型コースの代表

白く瀟洒なクラブハウス。決して豪華ではなく、深い森の中に佇む。
私が初めて同G Cを訪れたのは1987年、岡本綾子が全米女子オープンのプレーオフで敗れ、優勝を逃した2日後のことでした。当時のUSGA会長のJ・ハントから同GC会員のJ・マーシャル(国連大学学長)を紹介され、彼と一緒にニューヨークのホテルからニュージャージー州へと2時間、車を走らせました。道案内の看板などなく、いつの間にか敷地内に入り、裏側からクラブハウスへ到着。威圧するような進入路でもなければ、壮麗なクラブハウスというわけでもありません。ギシギシと軋む音のする2階ロッカールームへの階段は、歴史と伝統を感じさせるものではありましたが…。
コースはおよそ40万坪の鬱蒼とした松林に、18ホールがレイアウトされ、フェアウェイとグリーン以外は全て砂地のウェイストエリアと思ってよいでしょう。ウェイストエリアは人手がかからず、今でいうSDGs(持続可能性)を計らずも意図しているといえます。ティショットは200ヤードのキャリーがなければ、フェアウェイには届きません。未熟な技術にはペナルティをという、まさに可罰型設計の典型です。バンカーの数は無数で、途中で数え切れなくなったため、実際はどこまでが荒地か、はっきりしませんでした。
高い戦略性と独自性 忘れることがない18ホール
その日は2ラウンドプレーしたのですが、驚いたのは昼食時、18ホール、全てのホールをはっきりと覚えていたことです。パー3、パー5、上りに下り、左右のドッグレッグ、バンカーの配置は全て異なり、ティショットの狙いが全部違い、同じパターンが1ホールとしてないのです。「せっかくのチャンスだから頭に刻みつけておこう」と思っていたわけでもありません。それなのに、18ホールがしっかりと頭の中に刻まれていたのです。まことに不思議な感覚でありました。
おそらくここが、「世界一」のポイントなのだろうと思いました。どんな名コースをプレーして感銘を受けても、年月がたつと何ホールかは記憶が薄れて、バンカーやハザードの位置が判然としなくなったりすることが多々あるものです。

18番ホール(428ヤード・P4)は、巨大なバンカー越えのティショットで200ヤードの飛距離が求められ、グリーン手前には池が待ち受ける。
しかし同GCにおいては何十年たってもそんなことはなく、各ホールの戦略性、メモラビリティー、デザインバランスなど、他にない独自性に満ちていて、誰もが忘れ得ないコースとして記憶され、唯一無二として評価せざるを得なくなるからではないのでしょうか。
クラブとしては、メンズプライベートクラブで、以前は女子トイレもなく、ロッカールームでは裸のメンバーたちが歩き回っていました。しかしある時から日曜の午後だけ女性のプレーが許されるようになって、変わってきてはいますが…。
私がメンバーになれたのは突然でした。2013年、メリオンGCで行われた全米オープンではUSGAのレフェリーとして参加。試合が終わった次の日、USGAの理事だったP・キャッスルマンに同GCに連れて行かれ、もう翌日には「君は会員になったから」との宣託を受けたのでした。
語り尽くせないエピソードが物語るクラブの歴史と人の歴史
クラブとは何ぞや…、という問いに一つの答えを見たのは、同GCで75年史の巻末を読んだ時です。そこにはクラブで起きた様々な物語が書いてありました。アウトを38で回った後、10番パー3で38を叩いたチャンピオン、13番の右の林の中で行方不明になり、隣村から帰ってきたゲスト、バーディー、イーグル・ホールインワン、バーディーと続いた後、ハウスのバーに戻ってそのまま酔いつぶれてしまったスクラッチプレーヤー…etc。
それらの歴史的なエピソードを、若い会員たちがまるで見てきたかのように得意げに話すのは、同GCの伝統と言います。若い会員も1人のゴルファーとして入会し、そこに肩書は不要です。またそういう歴史と伝統を紡いでくれる若者を、積極的に仲間にしようという雰囲気が会員たちには満ちています。
結局、「クラブの歴史は人の歴史」だと、その巻末のエピソードは語っているのだと思います。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。