
新進気鋭のグローバルAIスタートアップが集結し、AIテクノロジーの未来やOSS企業の展望について議論しました。
- DX
- クラウド
- AI
- オープンソース
- イノベーション
- グローバル
- 新規ビジネス創出
- 業務効率化
- グローバル化対応
- 情報通信/放送
- 製造
- 流通/運輸
- 情報サービス
- 金融/保険
- 公共/公益
- 科学/工学
- 開催日
- 開催方法
-
会場(CIC Tokyo)/オンライン(Zoom Webinar)
- 共催
-
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、CIC Japan合同会社
オープンソース(OSS)とは、無償で⼀般公開されたソフトウェアおよびソースコードのことを指し、誰でもそのソフトウェアの利⽤や改良が可能です。近年、AI企業を含めたソフトウェア業界ではOSSを⽤いてビジネス展開する企業が急増しており、近い将来にはOSSがソフトウェア業界の新たなスタンダードになると予想されています。本イベントではOSS業界の中でも新進気鋭の世界的AIスタートアップが虎ノ⾨ヒルズに集結し、OSSとAI、そして日本市場の可能性について語りました。
580名を超える参加登録があり大盛況に終わったこのイベントのうち、本レポートでは主にパネルディスカッションの様子の一部をご紹介します。

パネルディスカッション概要
AI開発に携わるエンジニアやAIビジネスに関わる方を対象に開催された本イベント。パネルディスカッションでは、まず「オープンソースソフトウェア」をテーマに、各社にとってOSSはどんな意味を持つのか、次に「AIの未来」をテーマに、OpenAIを取り巻くマーケット展望やプライバシーとセキュリティの問題について、最後に「日本市場」について各パネラーによる議論が行われました。
パネラー紹介

数々のスタートアップでビジネス開発やエンジニア職を歴任し、エンタープライズ向けにフォーカスした世界初の商⽤Kubernetes企業を設立・売却した。その後、2018年に商⽤オープンソース(COSS)への出資に特化したOSS Capitalを創業。2019年にはCOSSのグローバルカンファレンス「Open Core Summit」を設⽴し、OSS業界のトップランナーとして広く知られる。

2020年5⽉にウィーン⼯科⼤学でコンピュータサイエンスの博⼠課程を修了。⼩さな線⾍をモデルとした新たなAIニューラルネットワーク「リキッド・ニューラル・ネットワーク(LNN)」を発表。その後、マサチューセッツ⼯科⼤学(CSAIL,MIT)で研究を発展し、国際的な評価を受ける。2023年にLiquid AIを設⽴。LNNは革新的なAIモデルとして期待されている。TEDxスピーカーとしても活躍。

⽶スタンフォード⼤学⼯学部経営⼯学科卒業後、バークレイズ・キャピタル証券(現・バークレイズ証券)に就職し、東京勤務。その後、中国北京にて証券⾃⼰勘定取引会社を設⽴・経営。会社売却後、MBAを取得。Googleやスタートアップで機械学習・データ分析の要職を歴任。その後、画像生成AIモデルのStable Diffusionで世界にインパクトを与えたStability AIに参画、2023年に⽇本⽀社を設⽴。

元グーグルのエンジニアで、2017年に論文「Attention Is All You Need」を発表。この論文では、自然言語処理のための「トランスフォーマー」と呼ばれるディープラーニングモデルを紹介し、ChatGPTのような最先端AIシステムのバックボーンとなった。同じく元グーグルのデビッド・ハー氏、元メルカリの伊藤錬氏と共に2023年8月にsakana.aiを日本で創業。
モデレーター紹介

2003年入社。SEとして通信キャリアを担当後、2010年にシリコンバレーに赴任。商材開拓担当を経て、現地営業・技術チームを立ち上げ。Cloud Nativeやオープンソース分野など、米欧スタートアップとのパートナーシップによる事業推進。現在は、自社開発クラウドサービス「PITWALL」の開発責任者として、グローバル市場に挑戦中。
パネルディスカッション
テーマ1:OSSとは
パネラー全員がOSS業界のプレイヤーという共通点があり、まずはオープンソースとは何なのか、なぜその形態を選んでいるのかというテーマからパネルディスカッションがスタートしました。

「OSSとは、イノベーションのための方法論であり一つのアプローチです」
最初に答えたのはOSS Capitalの創業者でありOSS業界に精通したジョセフ ジャックス氏。
OSSとは一般的にソフトウェアソースコードに用いられる考え方ですが、今はAIを筆頭に先端テクノロジーはその枠を超え、科学的あるいは数学的アルゴリズムにもオープンソースの考え方が広がっていることが紹介されました。
さらにLiquid AIのラミン ハサニ氏は
「OSSとは科学的なアプローチのことを指し、製品やビジネスモデルと同一に語っては危険」であるし、「私たちは科学的進歩のためにOSSを選択し、そのことを前提にどのようにマネタイズしていくのかを考えていくべきだと思います」
と語られました。
ディスカッションの中では、とりわけMeta(旧Facebook)の事例について語られ、LLaMA※1がオープンソース化されたことで業界全体あるいはMeta自身が多大な恩恵を得られたこと、さらにOCP※2がデータセンターやクラウド基盤の運用効率を劇的に引き上げたことなどが紹介されました。
※1Meta社が2023年3月に発表したオープンソースの大規模言語モデル(LLM)
※2旧Facebook社が2011年4月に発足したサーバなどのハードウェアの設計図や仕様のオープンソース化を推進する非営利コミュニティ
テーマ2:OSSとビジネスについて
テーマ1でもOSSはビジネスの話と分けて考えられるべきだとの言及がありましたが、OSSに関連したビジネスは簡単ではないというのが一般的な見解です。そこでモデレーターの田中から、OSS業界のビジネスモデルの変遷について簡単な紹介があった後、将来の展望について再びジョセフ ジャックス氏が語りました。

「OSSをめぐるビジネスモデルの歴史はまだ浅く、レッドハットをその第一世代として、その後現れた企業のほとんどは、特定のプロフェッショナルユーザー向けにOSSのアドオン機能を有償提供しているというのが実態です。それはつまりOpenAIがAPIを有償提供しているのと同じ構図で、OSSに限らずほとんどのソフトウェア企業が同一のビジネスモデルであり、今後は大資本をもった企業もこのモデルを選択していくことになるでしょう。」

sakana.aiのライオン ジョーンズ氏からも以下のコメントが補足されました。
「オープンソースを適切に使うことができれば、ある意味ではクローズドソースになるのではないかと思います。つまりどういうことかと言うと、科学的なアプローチをオープンにすることで技術革新を進めることができ、コミュニティが大きくなっていく。すると今度は自社のビジネスで様々な恩恵を受けることができ、結果的にオープンソースの上に構築されたビジネスはシークレットソースとして独自の価値を生み出していくのではないかと思います。」
テーマ3:OpenAIについて
続いて各パネラーから個人的な生成AI活用方法について紹介があり、ビジネスの側面でOpenAIとは各社にとってどのような位置づけなのかというテーマに移りました。
「OpenAIは競合か共存か」
という問いかけに対しては、一部競合になり得る可能性もありながら、基本的には共存関係を望んでいるというのが全員の回答でした。
各社特色のあるスタートアップであり、Liquid AI社はエッジAIソリューションということでシステム開発や市場提供のアプローチがトランスフォーマーとは異なっていることを強調しました。
Stability AIのジェリー チー氏も、
「私たちのモデルとOpenAIのAPIを両方を使っているアプリやサービスがたくさんあります。テキスト生成にはChatGPTを使い、画像生成には私たちのモデルを使うなどの使い分けを行ったりしています。」と既に多くのエンジニアや事業者が自社のモデルとOpenAIのモデルを組み合わせて活用していることが紹介されました。

また、ジョセフ ジャックス氏とライオン ジョーンズ氏は口をそろえ、
「OSSコミュニティやそのムーブメントは今後も広がりを見せ、大手企業に対してもその流れは不可逆なものになっています。さらに、OSS業界にはここにいる方々のように革新的なアプローチを生み出す企業がたくさんあり、新たなゲームチェンジャーが登場することが予見されます。現在のように、数年にわたり一部の大手企業が特定の技術や市場を独占し続けるのは難しいでしょう」
と今後の展望について語りました。
テーマ4:セキュリティとプライバシーの問題について
次に、視聴者から事前に募集した質問のうち、特に関心の高かったセキュリティとプライバシーの問題に対する対応や方針について議論されました。
まず最初にラミン ハサニ氏から
「私たちは開発しているモデルそのものに説明可能性を追求しており、それはシステムを定量的に評価・分析したり、システムの堅牢性を担保することに繋がります」
とLiquid AI社のアプローチについて説明がありました。

既存の大規模な深層学習モデルは結果を導き出す過程において、何が起こっているのか人間が理解することは極めて難しく、説明不可能だと言われています。しかしイノベーションが進展するほど、その説明可能性の需要は高まっており、ラミン ハサニ氏をはじめ様々な科学者が研究を進めているとのことでした。
またプライバシー保護の観点から近年注目されている差分プライバシー※3技術についても紹介されました。差分プライバシー技術とはモデルの開発や学習時にあらかじめ統計情報を乱雑化するコードを組み込んでおくことで、モデルの精度を落とさず高い匿名性を担保できるもので、日本企業からの関心も非常に高まっています。
さらにライオン ジョーンズ氏からは、
「AIの危険性について十分に認知・教育されていないことを危惧している」
とAI教育の課題について言及がありました。
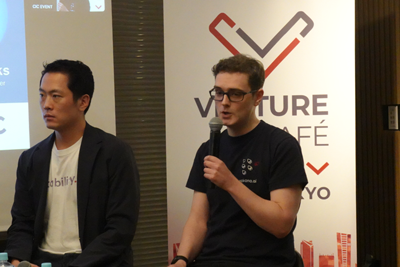
インターネット上には既にAIで生成されたコンテンツやフェイクで溢れており、本物を見分けることは難しくなっています。学生やクリエイター、ジャーナリストあるいは消費者にとってはその出自や権利を証明できることが非常に重要であり、各社でもその問題解決に向けた取り組みが開始されているとのことでした。
※3データセットの一部の情報を入手できた場合、その差分情報から別の対象者の個人情報を特定できてしまうような弱い匿名性が成り立っている状態のこと
テーマ5:日本市場について
最後に、日本市場についてどう見ているか、日本市場に何を期待しているかをパネラーにお話いただきました。
ライオン ジョーンズ氏
「私たちは日本で起業しましたが、なぜ日本なのかとよく聞かれます。まず個人的に東京の人々や安全性、食文化が好きなのでここにいたいと思っています。そして困難と言われていたシリコンバレーのVCからも資金調達をすることができ、今のところ研究開発も順調なので後悔はありません。さらに東京をアジア全体のAIマーケットのハブとして盛り上げていきたいと考えています」
ラミン ハサニ氏
「日本国内の才能と革新的な技術に対し深い敬意があります。特に東京大学や国立情報学研究所、理化学研究所にいる方々の才能と交流は、私たちのプロジェクトにとって不可欠な要素です。MITに匹敵するものが日本にはあります。さらにCTCともビジネスパートナーとして良好な関係を築いており、今後日本のスタートアップや大企業と共にプロジェクトを進められることにワクワクしています。」
ジェリー チー氏
「日本にはクールなゲームやアート、デザインを生み出すクリエイティブな企業や人材が豊富にいます。例えば、メディアや広告、エンターテイメント、アニメ業界であり、デザイナー、ミュージシャン、アーティストです。彼らと私たちのAIモデルは非常に相性がいいのです。」
また最後に、ジョセフ ジャックス氏からも海外投資家目線で、「外国の資本や人材の流入が増えている背景には、日本がイスラエルと並ぶ、世界で最もAIフレンドリーな規制環境が整っており、革新的な取り組みに対して開放的である点が魅力的だ」ということで、パネルディスカッションを締めくくっていただきました。

この後、予定時間を超えるまで会場との質疑応答が続き、大盛況のままに本編を終了しました。
