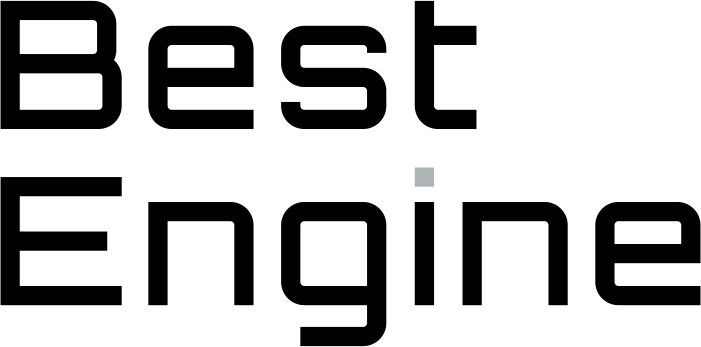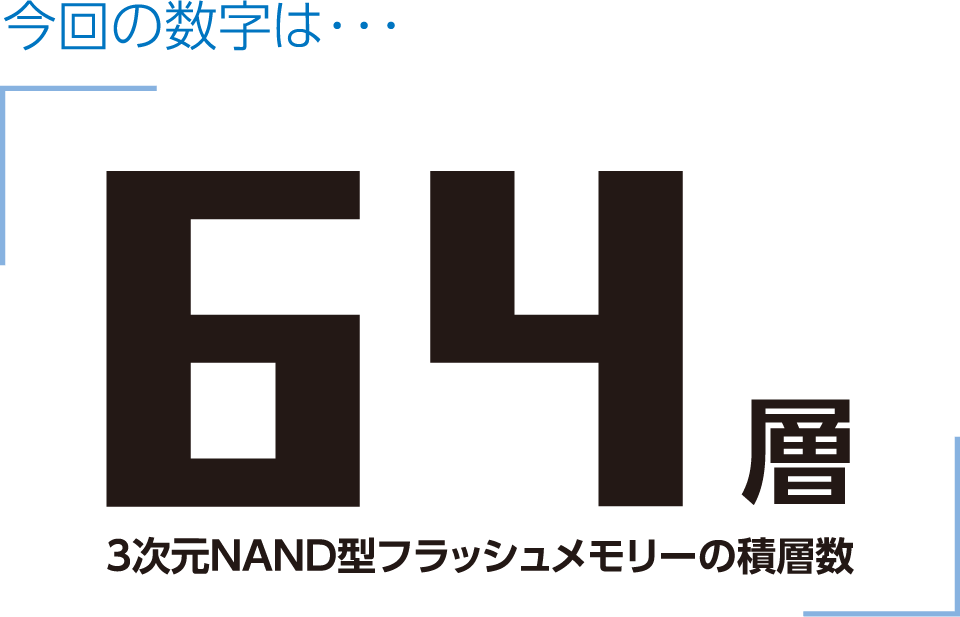数字で見る IT Insight
朝日新聞
経済部 記者
鈴木 友里子
2008年朝日新聞社入社。
青森総局、三沢支局を経て2013年から東京本社経済部。経済産業省等を担当し2015年から電機・IT企業を担当。
AIやIoTの普及が進む中、ますます需要が高まるのが記憶媒体だ。多くの情報を取得し分析・活用するには、情報の受け皿が必要になる。その役割を担う半導体の記憶装置で主役となりつつあるのが「3次元NAND型フラッシュメモリー」だ。
NAND型フラッシュメモリーは、ハードディスクドライブに比べて書き込みや読み取りが速く、衝撃にも強いのが特徴だ。その中でも構造が「3次元化」したものを3 次元NAND型フラッシュメモリーと呼ぶ。
「3次元」とは言葉の通り、データを保存するシートが何層も立体的に積み上げられた状態のことを指す。データが入る小部屋「セル」が詰まったシートの枚数が多ければ多いほど、記憶できる容量も増える。実用化されているものでは、シートが48枚重なった「48層」や、64枚重なった「64層」の3次元NAND型フラッシュメモリーがある。ただ容量は単純に48倍や64倍になるわけではなく、例えば48層のもので2倍程度となる。
かつては1枚のシートにどれだけ多くのセルを作るかが容量を増やすカギだった。だが、セルを詰め込み過ぎるとデータ同士が干渉しあってエラーが起きる。その課題をクリアし、かつ大容量化を実現する技術が3次元化というわけだ。
ただ、シートを重ねて立体構造を作るには高い技術力が欠かせない。積層数が増えれば増えるほど難易度も上がる。NAND型フラッシュメモリーも、その3次元化も世界に先駆けて開発したのは日本の東芝だが、現在は韓国サムスン電子が一歩リードしている。世界シェアトップのサムスンは昨年末に64層の量産化に成功した。それを追うシェア2位の東芝は昨年48層の生産出荷を開始し、今年の上半期中には64層の量産化を目指している。更なる多層化へ向けた研究開発も進められており、東芝は今後100層まで増やす目標も公表している。
今、世界ではサムスンのほか、東芝と協業する米ウェスタンデジタル連合、米マイクロン・テクノロジーと米インテル連合、韓国SKハイニックスの計4陣営がしのぎを削っている。NAND型フラッシュメモリーは、SDカードやUSBメモリー、スマートフォンやタブレットのみならず、データセンターでも広く使われ始めており、小型化・大容量化のニーズの中で今後はますます利用が進むと予想される。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。