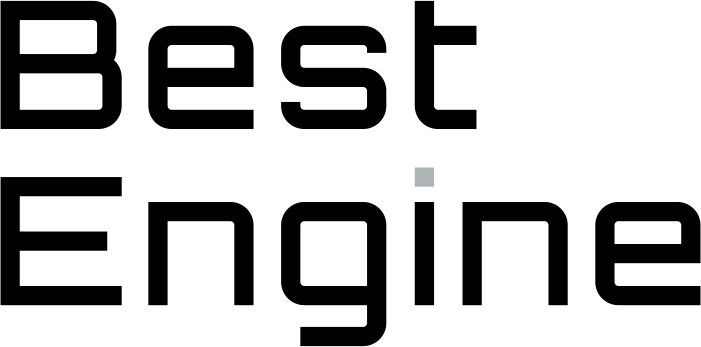IT Terminology
エッジコンピューティング
リアルタイムな処理はエッジが行う
ところで、クラウドコンピューティングが広く利用されるようになったのは、ここ10年ほどのことであり、それ以前は、端末そのものや端末近くのサーバでデータを処理するのが普通でした。とすれば、エッジコンピューティングと言っても、昔の方法に戻っただけなのでは?と思う人もいるかもしれません。しかし、そうではありません。
企業が自社運用のサーバを持ち、自前でデータの処理や計算を行うという状況が変化し始めたのは、2000年頃です。大容量のブロードバンドが登場し、社外の情報設備にデータ処理を外注することが可能になったためでした。その流れが拡大し、クラウドコンピューティングが一般的になっていく中で、自社の設備で情報を処理するという従来の運用形態は、クラウドと区別する意味で「オンプレミス(on premises=「敷地内で」)」と呼ばれるようになりました。
確かに、現在のエッジコンピューティングは、運用の形態としてはオンプレミスと似ています。では、その違いは何かと言えば、オンプレミスでは、あらゆるデータ処理をオンプレミスで行うしかなかったのに対して、エッジコンピューティングはそうではないことが挙げられます。つまり、リアルタイム性が求められる処理はエッジで行い、大規模な連携が必要な処理などはクラウドで行うという具合に、エッジとクラウド双方の特性を活かして作業を分散させることで、最も効率の良い処理方法を探れるのです。それがエッジコンピューティングの強みであり、オンプレミスとの大きな違いと言えるでしょう
Microsoftのナデラ氏も、前述の会合で次のように話しています。「これからは、エッジかクラウドかということではない。インテリジェントなエッジとインテリジェントなクラウドが手を取り合うという新しい時代が始まるのだ」と。オンプレミスの時代からクラウド全盛の時代を経て、その次の段階として、エッジとクラウドが持つそれぞれの強みを活かす時代が始まりつつあるのです。
エッジによってAIが進化する
冒頭のナデラ氏の言葉―コンピューティングの未来は、エッジにある―に戻ると、彼の言う「未来」の中心には、AI(人工知能)があります。500億の機器が生み出す膨大なデータが、エッジで処理された後に、クラウドに集約されてAIの学習に使われる。その結果、AIは、今とは比べ物にならないほどの飛躍を遂げ、世界を大きく変えるだろうと言うのです。
一体AIはどこまで進化し、その結果、世界はどのように変わるのか。エッジコンピューティングの広がりによって、その進化は今後、ますます速度を上げていくことになりそうです。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。