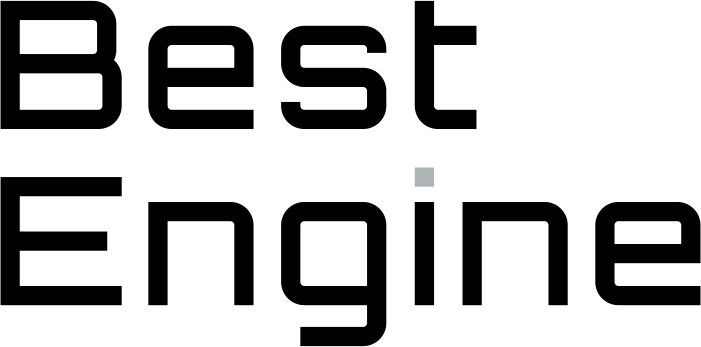|特集|英国Oxford Quantum Circuits Limited(OQC):特別インタビュー 量子コンピュータは、どこまで実用化に近づいたか
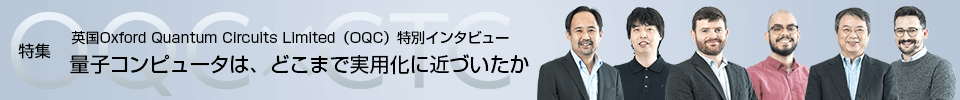
複数の方式が共存することの意味
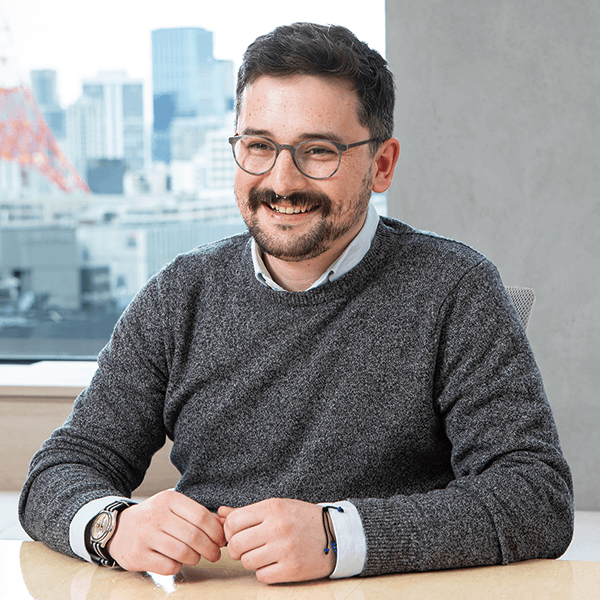
Jamie Friel
ジェイミー・フリエル
Oxford Quantum Circuits Limited
Compiler Team Manager
OQCのハードウェア上で問題を解決できる画期的な量子コンパイラを構築。
- ―――
- 量子コンピュータは現在、複数の異なる方式のハードウェアが開発されています。例えばAmazon Braket上では現状、3つの量子コンピュータにアクセスできるようになっていますが、そのうち、OQCのOQC Toshikoを含む2つが「超伝導方式」※3で、もう1つが「イオントラップ方式」※4です。
このように、異なる方式のハードウェアの開発が並行して進む状況は、今後どうなっていくと予想されていますか。 - Owen(オーウェン)
- 現在開発が進んでいる量子コンピュータはいずれも、「NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum Computer)時代のデバイス」と呼ばれます。ノイズがある、中規模のデバイスという意味で、言い換えると、いずれもまだ発展途上にあるデバイスだということです。そのため、それぞれに長所と短所があり、解決すべき技術的課題を抱えているのですが、私は、現在のように様々な方式のハードウェアの開発が進み、量子コンピュータのエコシステムが多様性を持つことは、非常に良いことだと考えています。それはかつてトランジスタが進化する過程で、多様性を獲得してきた歴史と重なります。
異なる方式の開発が進み、それぞれが発展することは、ユーザーにとって複数の選択肢が用意されることを意味し、さらには、この産業が今まさに拡大中であることも示しています。それぞれの方式が今後どう進化していくのか、私はとても楽しみにしています。
- Jamie(ジェイミー)
- 方式ごとの違いについて簡単に説明すると、例えば超伝導方式はスケールさせやすい、つまり量子ビットの数を増やしやすいという特長があります。結果、既存のスーパーコンピュータやデータセンター環境とも統合させやすいのが大きな利点となります。一方、イオントラップ方式はスケールするのは難しいものの、ノイズが少なく、量子ビットの質が良い。結果、より正確な計算結果を出すことに長けています。このように、量子ビットのスケールのしやすさか、質の良さか、といった点がこの2つの方式の違いの1つです。また超伝導方式は、ゲート速度が非常に速く、イオントラップ方式などに比べて計算時間をはるかに短くできるという利点もあります。
技術面、ビジネス面の課題解決を並行して進める
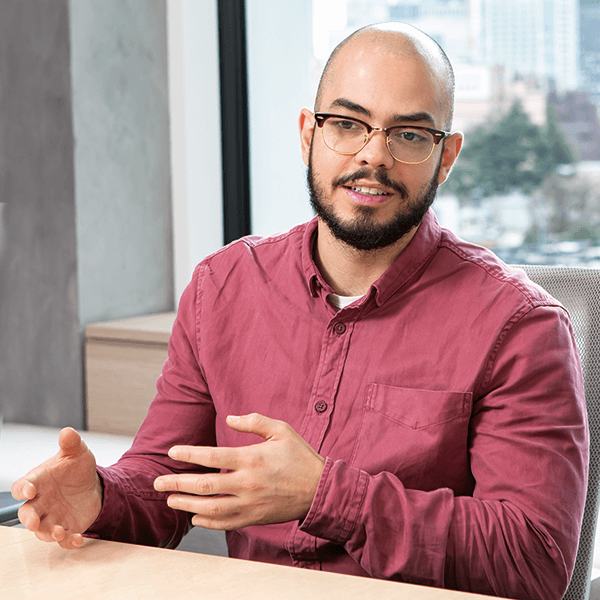
Rodrigo Chaves
ロドリゴ・チャベス
Oxford Quantum Circuits Limited
Algorithm Developer
ソフトウェアチームとハードウェアチームをつなぎ、最適な量子アルゴリズムを開発
- ―――
- OQC LucyやOQC Toshikoを開発する上で難しかったのは、例えばどのような点ですか。
- Owen(オーウェン)
- 超伝導方式の量子コンピュータを構築する際の課題の1つは、いかに低温冷却するかであり、私たちもその点で苦労しました。私たちは、絶対零度よりも数ミリケルビン高いだけという超低温を長時間保つ必要がありましたが、従来、そのような低温に保つことは数時間しかできないとされていました。そこで様々な工夫を重ね、徐々に長い時間、低温を維持できるようにしていきました。OQC Lucyは現在、超低温を保ったまま2年間稼働し続けることができています。
- ―――
- 現状ではどのような課題がありますか。技術的な課題、ビジネス上での課題、それぞれ教えてください。
- Rodrigo(ロドリゴ)
- 技術面について例を挙げると、1つには、いかに量子ビットの質を高めるかというハードウェア上の課題があります。OQC Lucyの開発時は、量子ビットの安定性を高めることが主な課題となりましたが、OQC Toshikoでは、その質をいかに高くするかという点を、今まさに追求しています。また、有用なアルゴリズムを作り出していくことも重要であり、私はその仕事に取り組んでいます。つまり、個別の問題に対して、量子コンピュータを用いて解く具体的な方法を開発することです。
- Jamie(ジェイミー)
- ソフトウェアの面では、いかにして、量子コンピュータを一般の人が使えるものにするかが最大の課題かもしれません。古典コンピュータ(=従来のコンピュータ)でもプログラミング上の難しさは色々とありますが、量子コンピュータの難しさはその上をいきます。私たちコンパイラチームが行っているのは、それをいかに簡単に使えるものにするかということです。現在の量子コンピュータのプログラミングは、かつて古典コンピュータのプログラミングがパンチカードを使っていた時代のように、とても原始的な状態です。古典コンピュータはWindowsの登場で飛躍的に使いやすくなりましたが、私たちは今、量子コンピュータにとってのそのようなソフトウェアを開発することに取り組んでいます。
- Owen(オーウェン)
- ビジネス上の課題について私からお話しすると、最も重要だと考えているのは、今まさに量子コンピュータを必要としている人が、この技術を活用できる環境をいかにして整えていくかということです。すなわち、解決すべき問題が既にあり、量子コンピュータがあればそれを解決できるという状況にある人をサポートし、量子コンピューティングの技術が実際に役に立つことを示していくことです。そのためにも、ロドリゴとジェイミーが話した技術的な課題を乗り越えることが重要であり、技術とビジネスを共に発展させていくことが肝要だと感じています。
- Jamie(ジェイミー)
- これらの課題を考えた時、今後CTCと一緒に仕事ができるのは私たちにとって非常に幸運なことです。CTCは、量子コンピューティングにおいて、短期的に必要となる技術や知見も、長期的なビジョンも併せ持つ、非常に先進的な組織だと感じるからです。
知っておきたい
量子コンピュータの用語
-
超伝導方式
量子コンピュータの方式の一つ。超低温に冷却して超伝導状態(電気抵抗がゼロ)にした回路によって量子ビットを実現する。IBMやGoogleが開発するマシンや、理化学研究所が開発した国産初号機もこの方式を採用している。
-
イオントラップ方式
量子コンピュータの方式の一つ。電場や磁場によって捕獲(トラップ)したイオン(+や-の電荷を帯びた原子のこと)を量子ビットとして用いる。大阪大学や沖縄科学技術大学院大学(OIST)など、国内でも複数の大学や研究機関で研究が進んでいる。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。