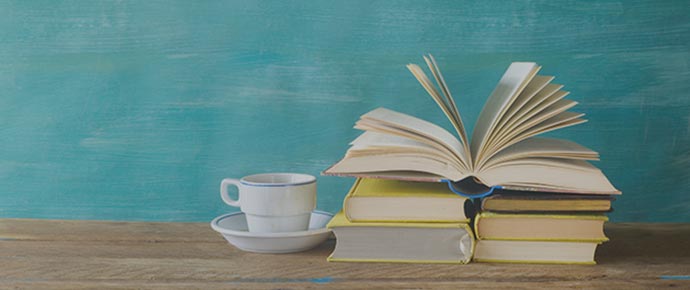進むシステム内製化。そのメリット&デメリットと内製化のポイントを探る
いま、「システムの内製化」が話題になっています。従来、SIerやベンダーなど、専門技術と知見を持つ企業がシステム開発を担っていましたが、それを「自社内で行う」のが、内製化です。今回は、システム内製化のメリット、デメリット、導入のポイントについて解説します。

システム内製化の背景とは
従来、日本企業の多くは、社内システムをSIerやベンダーに「丸投げ」していました。言うなれば「餅は餅屋」という発想です。しかし、いま多くの企業が「システムの内製化」に舵を切っています。その背景には、市場変化のスピードの加速、相次ぐシステム障害への対応、昨今のビジネスにおけるデータの重要性の増大が挙げられます。
システム障害の発生時にすべてのシステムが外注されていると、外注先との連絡に手間がかかり、障害への対応や復旧が遅れることがあります。中には「なぜ障害が起こったか?」の把握さえ、十分にできず、検証も行えないケースもあります。
また、市場の変化は加速し続けており、それに応じたシステムの刷新、改修は不可欠です。ところが、システムを外注しているとコスト的にも時間的にも、臨機応変な対応が難しく、市場変化への対応が困難になってしまいます。
こういった背景から、「システムの内製化」が進んでいるのです。
システムを内製化するメリットとデメリットとは?
前述したように、企業がシステム内製化を進める理由は明白です。しかし、あらゆることにはメリットとデメリットがあります。システム開発の内製化にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
メリット
システムの把握が可能になる
SIerやベンダーなどにシステムを外注していると、自社のシステムなのにその全容が把握できないといったことが起こります。内製化では、このような「ブラックボックス」が起こりにくいので、システムの内容、状況を把握することができます。
開発速度があがる
システムの開発、改修には、数ヵ月~年単位での期間を要します。社内で協議(仕様の決定)を行った上でSIerやベンダー依頼、仕様を検証してからスケジュール作成し、開発する必要があるためです。しかし、内製化をすれば、仕様決定から開発までの時間が短縮できます。
柔軟なシステム開発が可能
システム開発を外注していると、SIerやベンダーの都合も影響して、柔軟なシステム開発が困難になります。「仕様変更」はSIerにとって大きな負担であり、発注する側も仕様変更のたびに多大な追加費用を負担しなくてはなりませんでした。しかし、市場の変化は早く、開発中に仕様変更をせざるをえないケースも増えています。内製化していれば、外注する場合に比べて柔軟なシステム対応が可能になるでしょう。
人材育成、社内にシステムのノウハウが残る
システム開発を外注していると、社内にシステムについて熟知している人材がいない状態が起こりえます。ビジネスにおいてデータ活用の重要性が高まり、システムなしで仕事ができないいま、社内のIT人材の育成は不可欠です。内製化を行えば、社内の人材育成、システムに関するノウハウの蓄積も可能になります。
デメリット
システム品質の担保が困難
内製化する場合は、システム開発を専門とするSIerやベンダーに依頼する場合と比べて、技術、知識、ノウハウの点で、システムの品質が劣る可能性があります。
人材の確保・育成が困難
IT人材は市場で不足している状態です。システム内製化ではIT人材が欠かせませんが、その確保はなかなか難しいでしょう。社内で育成するためには、まず育成のノウハウを蓄積するところから始める必要があります。
システム担当者の離職リスクがある
内製化に成功したとしても、一部のシステム担当者に依存する状態だと、その担当者が離職した途端、システムの開発、維持、メンテナンスがうまくいかなくなってしまうことが想定されます。
デメリットを回避し、システム内製化を成功させるポイントとは?
メリット、デメリットがあるシステムの内製化ですが、成功させるポイントをあげてみましょう。
人材の確保ができるのか、育成できるのかを精査する
最大の課題の一つが、IT人材の確保、育成です。人材の採用や社内人材の育成ができる環境を準備できるかどうかを確認しなければなりません。現状、できないならば早急に対応を進める必要があります。
社内システムの棚卸し
現状、多くの企業では様々なシステムが社内で稼働しています。中には古くから稼働しているレガシーなシステムもあるでしょうし、一部業務だけで使われており、関係者以外は認知していないシステムもあるかもしれません。そういった社内のシステムをすべて棚卸ししておきましょう。システムの内製化といっても、すべてのシステムを内製化する必要はありません。高い安定性が求められる社内の基幹システムは内製化せず、変化が早いジャンルのシステムなどだけを内製化するといった判断も必要です。そのために社内システムを「見える化」しておくことが大切です。
社内開発できるツールの導入
自分でほとんどのプログラムコードを書けるIT人材は希少です。その育成にも時間とコストが掛かります。しかし、現在では、ローコード開発といってある程度のプログラムができれば、最低限のコード記述のみで高度はプログラムを組むことができるツールがあります。開発の時短にもつながり、内製化には欠かせないツールだといるでしょう。
ローコード開発ツール「OutSystems」は、ドラッグ&ドロップでのシステム構築の補助、システムの内容をビジュアライズされた状態でのシステム開発が可能。システムの内製化をサポートするツールです。
システム開発の内製化の手段として、ぜひ一度「OutSystems」をご検討ください。
▼システムの内製化に欠かせない、ローコード開発ツール
OutSystemsに関するお問い合わせはこちら