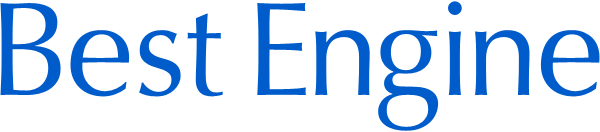Technical Report
データ分析及びシミュレーション活用による空港計画支援

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部
DSビジネス推進部
宮下 瞭
世界の航空需要は膨らみ続け、2019年に日本を訪れた外国人旅行客は約3,200万人、10年前の679万人に比べ、4.7倍になりました※。
旅客が増えれば、それに対応して空港も整備していかなければならず、具体的で説得力のある将来計画(空港計画)が必要になります。
ここでは空港計画の重要性とCTCの支援技術についてご紹介します。
訪日外国人の増加を見据え
2019年まで旅客数は上昇トレンドにありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現在、日本を訪れる外国人旅行客は減少しています。しかし、リーマンショックやSARSなど過去の状況を考慮すると、長期的に見れば上昇トレンドに戻ると考えられます。
世界中で航空需要が高まってきていることを背景に、航空旅客が年々増加しています。日本においても航空旅客は増加しており、今後もその傾向が続いていくことが見込まれています。また、政府が観光立国を宣言し、様々な観光資源に投資を行うことで、訪日需要の高まりを国内の観光に取り込んでいくといった動きも盛んです。訪日外国人旅客の目標も掲げ、2020年に4,000万人、2030年には6,000万人を目指すとしており、2019年の訪日外国人旅客は約3,200万人、その先には東京オリンピックの開催も控えていることから、更なる旅客の増加が予想されます。
様々なことが求められている空港
訪日外国人旅客目標を達成するならば、国内の空港を訪れる旅客は大幅に増加することになります。旅客が増えることは空港にとって非常に喜ばしいことですが、あまりに増えすぎてしまうと空港では様々な問題が起きてきます。
例えば、空港は建設時に年間旅客数を想定して設計されており、実際の運用で想定との大幅な乖離が発生すると、施設での待ち時間の増加など、旅客へ満足のいくサービスを提供することが難しくなります。実際、いくつかの空港では建設から時間がたっていることや利用者の急激な増加により、当初計画されていた施設規模に対して利用者需要の乖離が発生しています。
継続的かつ長期的な空港計画
これらの需要の変化に対応し、より戦略的に新たな需要を獲得するために空港も絶えず変化していく必要があります。しかし、空港が変化するのはそう簡単ではありません。なぜなら空港は一つの都市でもあり、関係各所や周囲の市区町村への影響が大きいためです。例えば、成田国際空港は約5万人の従業員を抱え、年間4,000万人を超える旅客が利用しています。空港を発着する航空機の騒音の影響は、半径約10kmにも及びます。また、国際空港であれば、国の外交的な戦略にも大きく影響を与えます。
そのため空港事業者は、将来計画を継続的かつ長期的な視点から作成し、多様な関係者に対して客観的にわかりやすく伝える必要があります。これを空港計画業務と呼びます。空港計画は主に短中期計画(数年後から10年後)と長期計画(10年以上)に大別されます。
更に国を代表するような空港の場合は、およそ20年から30年先の将来あるべき姿を描いた基本計画(マスタープラン)を作成します。マスタープランの作成には空港の基本的な経営方針や将来の需要予測、将来想定される国内外の様々な環境の変化を踏まえた上で、いつ・どの施設を・どの程度改修するべきかを見積もる必要があります。技術的、社会的課題も考慮すべきですし、資金回収計画や最終形までの移行計画、不利益を被る関係者への補填計画も考慮する必要があります。
近年は大規模空港だけでなく中規模空港においても、外国人旅行客の増加や施設の老朽化に伴う影響の評価など、より精度の高い説得力のある空港計画が求められるようになってきています。
- 【出典】「訪日外客数」日本政府観光局(JNTO)
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。