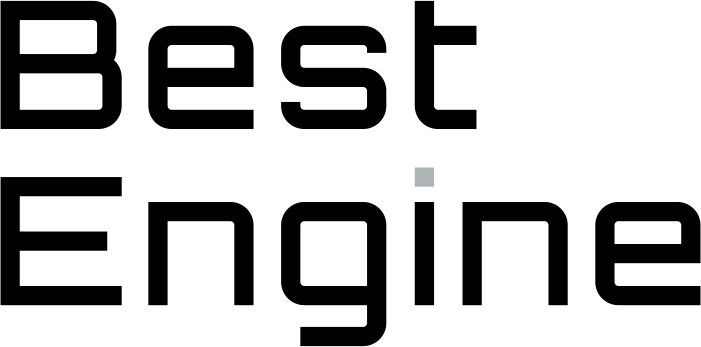|特集・対談|CTC approaches Generative AI ビジネスの未来を拓く生成AIの可能性

特集・対談 01
生成AIによる新時代の到来は大きなチャンス
独自の価値を生み出し続けるために
- ―――
- 生成AIがCTCのビジネスに与える影響は小さくないと想像しています。今、ビジネスの面でそれぞれが意識されていることを教えてください。
- 田中
-
現在のCTCは、顧客視点に立つとはいえ、お客様が実現したいことをご支援する、お客様が抱えている課題にお応えするために有用なソリューションを提供することが中心になっています。そのような仕事が今後も重要であることに変わりはないのですが、今後はお客様に応える形だけではなく、私たち自身が、自身の事業課題に対して取り組んだ経験資産を提供する重要性が高まると考えています。自分が主体となって何かを作り出す時は、他社へも適用できそうな汎用性の高い最大公約数的な選択肢ではなく、もっと自分たちの個別性に特化した、ある種尖った選択肢を取るものだと思います。
そこには、Why、What、Howが統合された価値が存在します。
生成AIが普及する時代に、私たちにしか提供できない価値を生み出し続けていくためには、そういう経験値をどれだけ蓄積し、ビジネスモデルに昇華できるかが重要になると考えています。 - 寺澤
- 生成AIの登場によって、プログラムを作るなどの開発工程が圧縮されることは間違いありません。その分、エンジニアのすべきことは変わります。より俯瞰的な視点を持つことが重要になります。例えば、今、教育現場でChatGPTを使うのはありかなしかといった議論がよく聞かれます。そういう時、ありを前提に考えた場合、どういう使い方なら有用か、と考えられるかどうかです。
一例として、小学校で「3+2」を教えるのに生成AIがどう使えるか。答えは言わずに考えるプロセスだけを提示する生成AIを作れば、教育現場でも有用ではないだろうか。
ではそれを作るためには、現在のLLMにどのようなチューニングを加えればいいのか。そして、そのような生成AIが登場した時、教員の仕事はどうなるのか――、といったところまで想像して、新しい提案ができるようなエンジニアが今後はますます重要になるでしょう。 - 田中
- 私たち自身が、日々、いかに自分たちの課題と向き合い、試行錯誤を重ねられるか。それが問われていると痛感しています。
研究・実験を重ね、ベストなサービスを提供
- ―――
- AIビジネスは、今まさに大きな過渡期にあることが伝わってきました。その中で、現在、CTCはどのようなサービスやプロダクトの開発に取り組んでいるのか、具体的な例を教えてください。
- 田中
- CTCグループでは、AIに関して多くの取り組みを行っています。その中で、今、私たちの部が取り組んでいることの一つに、CTC独自の視点で開発するプロダクトビジネスがあります。
「PITWALL」というプロジェクト名称で、システムの開発・運用現場の課題解決に寄与できるクラウドサービスを作っています。各企業の開発・運用の現場では、様々な管理ツールが使われており、個々のツールは高度化しているものの、肝心のインシデントが発生した際には、それらのツールを手作業で切り替え、各部署が連絡を取り合って対処しており、生産性や対応時間の長期化に関わる課題、対応者によるばらつき、一部のエキスパートがいなければ対応できないような属人性の課題を抱えています。
これらに対し、様々な状況下で、必要な情報にワンクリックでアクセスできる状態を作るための技術開発にチャレンジしています。今後の取り組みでは、情報の分析にディープラーニングを利用し、分析結果と人間をつなぐ部分には生成AIを利用していく予定です。 - 寺澤
- 私たちAIビジネス部が特に注力しているのは、2023年にスタートした生成AI関連の各種サービスです。5月に始めた「生成AIアドバイザリサービス」では、生成AIに関して基本的な検討から実装まで、様々な形でお客様の要望に応え、サポートするサービスです。そして8月には、「AOAI環境構築サービス」を開始しました。
これは、マイクロソフトが提供する生成AIサービス「Azure OpenAI Service」を利用して、企業ごとの独自な目的に合致した生成AIの環境を構築するサービスです。今、「自社のことを熟知したChatGPTのような生成AIが欲しい」という要望がすごく多いのです。「従業員の様々な質問に答えてくれるエキスパート的なコンピュータを作りたい」「一般消費者からの各種問い合わせに的確に応答できる生成AIが欲しい」など、こうしたご要望に対して、ChatGPTの検索機能などをチューニングし、社内文書の内容を学習させ、独自の生成AI環境を構築する。
それがこのサービスです。これまで実証実験を重ねてきて、幅広い要望に応えられる体制を整えたことに加え、セキュリティ面も万全を期しています。
今は連日、こうしたサービスへの対応を中心に行っており、その中で、私たち自身も生成AIの知見を、日々、深めています。 - ―――
- このサービスは今後、どのように展開していくのでしょうか。
- 寺澤
- 現状では、先ほど申し上げた、答えを教えないChatGPTのような特殊なものをご提供するのは困難です。
それを作るためには、ChatGPTではないオープンソースのLLMなどを活用して、我々でチューニングし、再学習を行わせることが必要です。さらに一歩踏み込んだ要望に応えられるようなサービスの構築に、これから着手すべく尽力しています。 - 田中
- 現状のベストチョイスは何かをしっかりと把握し、お客様にベストな提案をすることが求められます。そのために、私たちと寺澤さんの部隊では、次々に出てくる新たな生成AIの特徴を理解するために、例えば、独自に日本語の設問集を作って、応答の正確性、自然さを試すことなどにも取り組んでいます。
現状ではChatGPTが圧倒的な存在感を持っていますが、今後もそのままとは限りません。今ベストなものを活用して、しっかりとビジネスにつなげながらも、将来、私たちがどうしていくべきかを見極めるために、自らの課題に取り組み、経験資産も併せて、ベストな提案ができるよう、私たち自身が進化していくことを心掛けています。
生成AIの登場は飛躍のチャンス
- ―――
- 最後に改めて、生成AIが誕生した時代において、CTCの果たすべき役割やミッションは何か、教えてください。
- 田中
- 通常、新しい技術は、まずある業界で使われ出して、それが徐々に伝播していく形で普及します。ところが生成AIの場合、全ての業界に一気にドンと入ってきた。つまり、これまでのように、「こういう新しい技術があるので使ってみませんか」では足りず、私たち自身が、生成AIを活用して新たな価値を生み出しているということを示していかなければなりません。
CTCの力が問われる今だからこそ、飛躍のチャンスだと思っています。 - 寺澤
- 田中さんと同感です。生成AIは、まさに一気に下りてきた。ただ我々はかなり早くから動いていたので、これからもこの分野をリードしていける自信があります。私たちがこれからどんなサービスを作り出していくか、ぜひ見ていただければと思います。
NeuCraft
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。