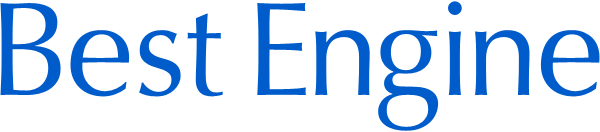IT Terminology
Web 4.0
情報の分散化を目指すWeb 3.0
そのような背景のもとに登場したのが、Web 3.0です。一極集中している情報を分散化させ、極度に中央集権化されつつあるインターネットの在り方を変えることを目指して提唱された概念だと言われます。その概念を実際のインターネットに落とし込むことを可能にしたのがブロックチェーンという技術でした。
ブロックチェーンとは、ネットワーク上でつながっている複数のユーザーの端末が、情報を分散して管理することを可能にする技術です。各種取り引きの履歴が複数のユーザーの端末に記録されるために、情報の改竄が極めて困難なことで知られ、ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)を支える技術となっています。
GAFAMが巨大な力を持つWeb 2.0の時代は今も継続しています。その中で、Web 3.0的なサービスが徐々に広がっていくことで、インターネットの在りようが少しずつ変わろうとしている。それが現在のインターネットの状況だと言えるのかもしれません。
ただし、Web 3.0という言葉を巡っては今も多少の混乱があります。Web 3.0には、実は、もう1つ別の意味があるからです。先に述べた意味でのWeb 3.0は、暗号資産の1つであるイーサリアムの共同設立者、ギャビン・ウッドが2014年に提唱したものですが※2、それとは別に、「Webの父」とも呼ばれる科学者のティム・バーナーズ=リーが、より以前に提案したWeb 3.0という語があるのです。
後者のWeb 3.0が指しているのは、コンピュータ自身が、データを単なる文字や数字の塊としてではなく、その意味を解釈して処理できるようになるインターネットの段階のことでした※3。もともとWeb 1.0、Web 2.0の流れに続くのは、こちらの方のWeb 3.0だったのですが、そこに、分散化を軸としたWeb 3.0という語が新たに提唱されたことで両者が混同され、Web 3.0というものがますますわかりにくいものになってしまったと考えられます。ただ最近のメディアを見る限り、Web 3.0というと、分散化を軸にした概念として考えられることが多いようです。
いずれにしても、Web 3.0におけるそのような混乱が続く中で、Webやネットのさらなる進化に伴って登場したのがWeb 4.0という概念なのです。
Web 4.0は「人間と機械の共生」の段階
Web 2.0は双方向性、Web 3.0は分散化といったキーワードがある中、Web 4.0が語られる時によく出てくるのはsymbiotic、すなわち「共生的」という言葉です。それは「人間と機械の共生」を指しています。Web 4.0が何かというのはまだ未確定ながらも、そのイメージは共有されつつあるようです。そして、それを実現する技術として最も大きな役割を果たすのは、やはりAIだろうと考えられます。
人間と機械の共生、そしてAI。そう聞いておそらく今、多くの人が思い浮かべるのは、ChatGPTではないでしょうか。
ChatGPTは、アメリカのOpenAI社が2022年11月に公開した、AIを利用したチャットサービスです。あらゆる問いに対して、あっという間に自然な言葉で的確に返答してくる力に驚愕した人は、読者の中にもきっと少なくないでしょう。このような、いわゆる「生成AI」の登場が、今後世界を大きく変えることはおそらく間違いなさそうです。
ChatGPTは、人間と機械が共生するとはこういうことなのかもしれないというイメージを、初めて具体的な形で示した「機械」のように思います。その自然な受け答えを見ると、私たち人間の思考もChatGPTとそう遠くない仕組みで成り立っているに過ぎないのかもしれない、人間の思考とは何なのだろう、などと思わず考えさせられます。
この先来たるWeb 4.0の時代、私たちは、機械と共に生きる中で、「人間とは何か」という問いをかつてない形で突き付けられるのかもしれません。
- ギャビン・ウッドが提唱した概念は、元来「Web3(ウェブスリー)」と表記されます。そのため、Web3と書かれる場合は通常こちらの概念を指します。一方、Web 3.0と書かれる時は、いずれの概念にも用いられるようです。
- ティム・バーナーズ=リーは、このような、コンピュータ自身がデータの意味を解釈・処理することをできるような枠組みを「セマンティック・ウェブ(semantic web)」と呼び、それを彼のWeb 3.0の中心的な構成要素としました。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。