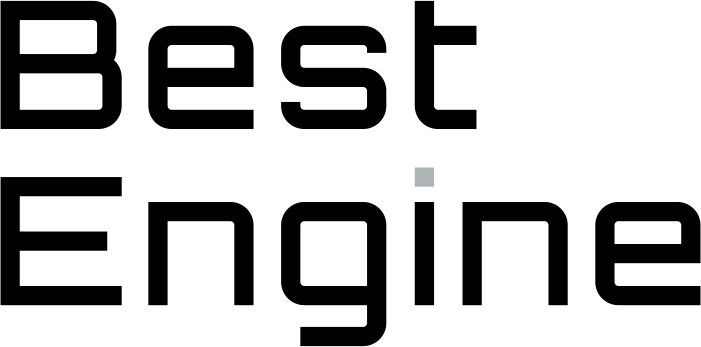|特別対談:1|生成AIの登場をチャンスにするための経営とは

「ビフォーAI」と「アフターAI」
- ―――
- AIの導入が進むと人間の業務は大きく変わると思われます。社内の舵取りについては、経営者はどのようなことを意識するべきでしょうか。
- 入山
- 経営共創基盤のCEOの冨山和彦さんが、著書の『ホワイトカラー消滅』の中で「仕事がこれからスマイルカーブ化する」とおっしゃっています。つまり、仕事を上流、中流、下流と分けた時、真ん中の中流の価値が下がるということです。上流は経営で、下流は現場。その両者をつなぐ中流の仕事はAIが得意とするところであり、それがAIに置き換えられていくからです。そのため大事なのは、現在中流にいる人をシフトすることですが、上流は経営層で人数が限られているので、下流へ移ってもらいたい。しかし、例えば25年間財務畑にいた人に「現場に行って交渉などをやって欲しい」と言ってもそれは簡単ではありません。ここが今後、日本企業の最大の課題になると私は考えています。このシフトができる会社は強いし、現在中流が膨れ上がっている会社は、これから大変だと思います。
- 新宮
- CTCは、エンジニアが7、8割を占める会社で、まさに彼らの仕事が今後AIによってどう変わっていくかというところを我々は今考えています。
- 入山
- CTCのエンジニアの多くはおそらく、お客様の所に行って課題を聞き出してソリューションを提案するなど、AIには代替できない現場の仕事をされているのではないでしょうか。またはプライベートAIの時代になったら、お客様の所にある非デジタルのデータを構造化して、価値を高めるといったことを一緒に進めていくことになるのではないかと想像していますが、それは人間にしかできない仕事です。一方、コーディングそのものはAIによってかなり効率化が進むとすると、エンジニアの方は、より人間にしかできない仕事に軸足が移るのではないかと思っています。
- 新宮
- 同様のイメージです。今後AIの導入が本格的に進めば、今までエンジニア10名で担当していた案件が5名でできるようになる、といった変化が起きるだろうと考えています。CTCのエンジニアは皆、生成AIの活用に積極的で、どんどん新しい技術を取り入れて効率化を進めています。その結果、人手不足という課題が解決でき、以前より多くのお客様の力になれることを目指しています。AIを会社の課題解決のツールとして活かす方法が見いだせると、さらにAI導入が進んでいくのだと、社内を見ていて感じます。
- 入山
- それはとても重要な流れだと思います。今、日本で注目されている会社の1つに、AIを活用して美容家電などのD2Cブランド事業を行うベンチャーがあります。2023年度の売上が70億で、24年度は142億、25年度は280億円という予想を掲げている会社ですが、従業員はまだ30人以下です。今後、AIが当たり前となる「アフターAI」の時代には、このような会社がきっとたくさん出てきます。こうしたAIネイティブの会社は、組織の構造も社員1人が生み出す価値も、「ビフォーAI」とは全く違う。「ビフォーAI」時代の会社は、今後相当な変革が迫られる時代に入っていくと思います。
- 新宮
- 本当に私たちは今、凄まじい変化の時代の真っ只中にいることを感じさせられます。しかしそうした時代にいることをチャンスと捉え、ますます積極的にAIと向き合い、これまで以上にお客様に求められる企業へ成長しなければと思います。

生成AIはインフラになる
- ―――
- 今日はたくさんの貴重なお話をいただきました。最後に改めて今日の対談を振り返って、生成AI時代への展望や読者へのメッセージをいただければと思います。
- 新宮
- 本日は改めて、AIの現在地と未来、日本の課題や進むべき道について、多くの視点をいただきました。最後にもう一点当社の話を付け加えると、CTCでは今、生成AIの利用規定や倫理規定の作成に力を入れています。2年ほど前、まだ生成AIについてわからないことが多かった頃に作ったものはルールが若干ガチガチで、現場からはもっと生成AIを使いやすくして欲しいという声が上がるようになりました。そうして今年、より現状に即したものに改定しました。機密性の高いデータの扱いについてはルールを厳格に保ち、それ以外のデータは基本的にオープンにしてメリハリをつけています。そのように、AIとの向き合い方を常に自ら問い直しながら、これからも最先端を走って行かなければと、今日、入山先生のお話を伺って思いを新たにしました。そして日本企業がそれぞれAIを自由に使いこなし、生成AI時代にも活躍し続けてもらえるよう、CTCはますます力を尽くしていくつもりです。
- 入山
- 先日、ジェイ・B・バーニーさんという有名な経営学者と対談をしたのですが、彼は最近、共著の論文で「生成AIは企業の持続的な競争優位の源泉にはならない」と書き、大きな反響を呼びました。それはなぜかと言えば、まさにインターネットと同様に、生成AIはいずれ、誰もが使うインフラのようなものになるからです。その結果20年後くらいには、きっと今は想像もできないような社会が形成されているはずであり、そう考えると、もはや生成AIを使うか使わないかを議論する段階ではありません。
日本は現場が強い国なので、生成AIをうまく使いこなせさえすれば、今後の可能性はすごく大きいと思います。そのためにも日本企業には、生成AIをとにかく道具として使い倒すんだという意識改革をどんどん進めてもらいたいと、新宮社長とお話しして改めて思いました。なかなか一歩を踏み出せないという会社は、私が申し上げるのも恐縮ですが、ぜひCTCと手を組み、CTCの力をうまく活用して、変革への一歩を進めてください。こうした取り組みが広がることで、日本全体の変革にもつながっていくことを願っています。本日はありがとうございました。 - 新宮
- 心強いお言葉に力をいただきます。ありがとうございました。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。