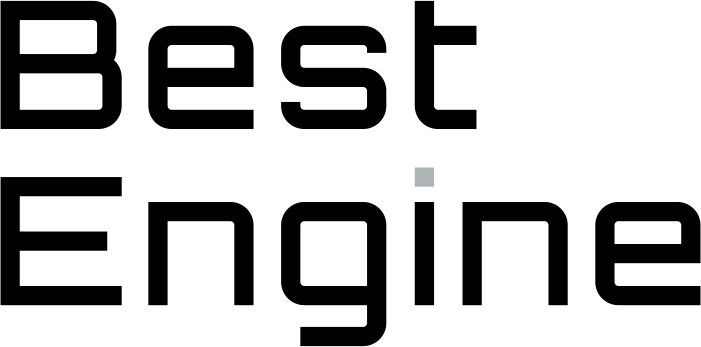|特集|“ポストトゥルース”時代における情報への向き合い方と発信術

“ポストトゥルース”時代到来の理由
- ──
- 今は“ポストトゥルース”の時代と言われます。事実かどうかが定かではない主張が力を持ち、それによって世の中が動くのが世界の潮流になりつつあります。なぜそのようになったのだと考えますか。
- 浜田
-
皆、見たくないものを見なくなっているということなのではないでしょうか。日本でいえば、ここ30年ほど、格差も広がり、多くの人が様々な不安を抱える時代になっています。そんな中で、自分の不安を刺激されるような現実を見たくないという気持ちになる人が多いのではないかと思います。日本の場合、それが顕著な形で表れているのがジェンダーの問題です。
例えば、女性のセクハラ問題など、現実としてそういう問題を報じても、「そんなの嘘だ、そんな差別聞いたことがない」と言われてしまう。そこには、女性が活躍することによって自分たちのポジションが脅かされるのではと不安を抱く男性たちの気持ちが見え隠れします。貧困に関しても同様のことが起きています。貧困で苦しんでいる人が声を上げた時に、「そんなの嘘だ」という声が上がるのですが、それは、貧困になるかもしれないと不安を感じている人が、現実を見たくないという裏返しなのかもしれません。そして今は、アルゴリズムの力で、誰もが知らないうちに自分にとって心地良い情報ばかりに囲まれがちで、事実に目を向けないことが可能になっています。それがポストトゥルースを生み出した要因だと考えています。 - ──
- その状況に対して、私たちはどうすれば良いのでしょうか。
- 浜田
-
今は、ちょうど時代の大きな転換期にあると言えます。
女性の地位、雇用の形態、産業構造…。長年続いてきたことが、いずれも大きく揺らいでいます。その現実を認めたくない人たちが、ポストトゥルースへと流れていると私は考えていますが、特に中高年世代の意識は、簡単には変わらないでしょう。この状況が変わるためには、世代交代を待つ必要があるように思います。もちろん、中高年世代にも若い世代にも、色々な考え方の人がいるのは前提として、全体として見れば、若い世代は、上の世代より柔軟だと言えるでしょう。環境問題に対して立ち上がったスウェーデンの10代の環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが象徴的ですが、今後その世代が中心になっていくことで、ポストトゥルースの次の時代へと進むのではないかと思っています。
オウンドメディアはどう作れば良いか
- ──
- 様々なメディアが林立する中、企業もまた、「オウンドメディア」と呼ばれる自社メディアを作って発信しています。この時代、企業が効果的な発信を行うためには、どのようなことを意識するべきだと考えますか。
- 浜田
-
企業のオウンドメディアには主に3つの機能があると思います。リクルーティング、コーポレートブランディング、そしてマーケティングです。目的によって、コンテンツの作り方やアプローチの仕方も違ってきますが、重要になるのは、紙とウェブの特性の違いをよく理解して、目的に応じた発信をすることだと思います。紙の広報誌であれば、やはり雑誌と同様にパッケージであるという性質から、読む人は限定されるものの、自社の価値観は伝えやすいでしょう。一方ウェブだと、不特定多数の人に読んでもらえる可能性はあるけれど、その企業やオウンドメディアのことを知らない人が読んだ場合にどういう印象を受けるかを意識する必要があります。今や企業のオウンドメディアも一般のメディアも、ウェブ上では同じ意識で読まれます。それゆえに、どこまで自社の宣伝的なことを入れるべきなのかを吟味し、クオリティも既存のメディアと競争できるレベルにまで高めないといけなくなっていると感じます。
- ──
- ウェブのオウンドメディアを持つ企業も増えていますが、効果的なサイトを作っている企業は多いと感じられますか。
- 浜田
-
クオリティが高く、多くの読者を集めているウェブのオウンドメディアも複数出てきていますが、おそらくその数は限られています。逆に、作ってもなかなか読まれないという悩みを抱えているところが多いのではないでしょうか。広く読まれているサイトは、外部配信のルートを持っている場合が多いと感じます。つまり、一般メディアのコンテンツの一環として転載してもらうのです。BIJでもいくつかのオウンドメディアの良質なコンテンツを転載していますが、やはりそのような出口を持っていると格段に読まれますね。また、これは紙でもウェブでも同様ですが、メディアを作る際、外部に丸投げするのではなく、その企業の内部の人が積極的に関わることがとても大切です。編集では素人でも、中の人が、どういう目的のためにどういうメディアを作るのかをしっかりと決めること。特にリクルーティングを目的としたオウンドメディアについては、人事部の人がしっかりと関わって作ったものが成功しているようです。
- ──
- 一方、今後も紙のオウンドメディアでやっていくという選択にも利点はありますか。
- 浜田
-
BtoBで顧客にしっかり届けたいという場合は、紙の方が有利にも思います。ウェブサイトのリンクを送っても、おそらく大半の人は読みませんが、紙のものが届くと、パラパラとだけでも開く人が多いのではないでしょうか。そうして少しでも、確実に読んでもらえるという良さは、紙の方にあるのですよね。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。