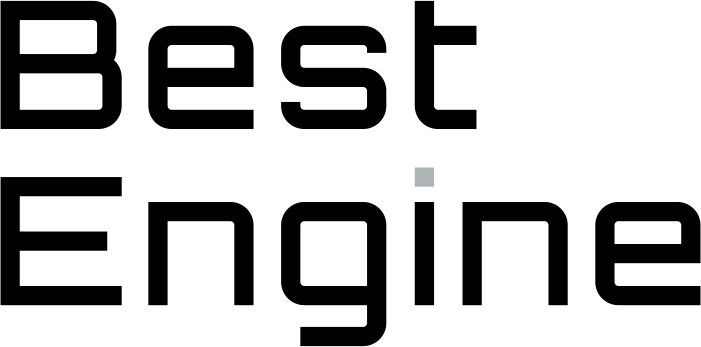|特集|50周年の節目にエンジニアたちが本音で語る、CTCの「今」と「これから」

自ら手を動かし、積極的にチャレンジできる環境を

久保田 さえ子
新事業創出・DX推進グループ
未来技術研究所長
データベースからデータウェアハウス、ビジネスインテリジェンス(BI)などの分析ビジネスを経て、近年は人工知能(AI)ビジネスに携わる。2022年4月より現職。

富士榮 尚寛
広域・社会インフラ事業グループ
西日本技術統括事業部 西日本ビジネス開発部
部長/エグゼクティブエンジニア
幅広い領域でのシステム開発の経験を持つ。クラウドを活用したAPI開発を中心に、現在は、デジタルアイデンティティに関わる新規ビジネスを統括。
- 里見
- それぞれCTCでエンジニアとして仕事をされてきた中で、良い点と悪い点を含めて、色々と感じてこられたと思います。今日は皆さんから、CTCをより良い会社にしていくためのヒントをいただけたらと思っています。CTCの課題や、もう少しこう変えていけたらと思う点、または、CTCは今後どういうところを強みとしていくのが良いか、といったことについて、ぜひ率直なご意見を聞かせてください。
- 久保田
-
最近私が感じているのは、もっと自ら手を動かしてチャレンジをしようという雰囲気があっても良いのでは、ということです。元々CTCは、自ら開発を行うことでベンダーよりも詳しいと、ベンダーから一目置かれるようなエンジニアがたくさんいた会社だったと思います。しかし近年、様々なITの機能がサービスという形で溢れていて、分業が進んだこともあり、開発経験の機会が少なくなっているように感じます。新しいことにチャレンジするには、自分がある程度試行錯誤できないとなかなか一歩を踏み出せない。私たち未来研も、“破壊的イノベーション”というスローガンを実践するために、そこから変えていきたいと思っています。続々と出てくる新しいテクノロジーを活用し、各人がそれぞれ自分の手を動かし、頭を悩ませて、新しい課題を解決していこうとする雰囲気をより高めていきたいですね。
- 富士榮
-
私が入社した時代はまだ、社内で自ら開発するという風土がしっかりと残っていました。CTCのエンジニアなら自分でソースコードから書くのが当たり前だと言われてきました。2000年代の前半ぐらいからでしょうか、徐々に会社の規模が大きくなり、エンジニアの人数が増え、大規模なSIプロジェクトを受注するようになったためプロジェクトの管理能力が重要視されるようになりました。そういった背景もあり、会社としての力点がマネジメントに移り、自社で作る機会が減ってきた気がします。私自身は大阪にいて、東京とはまた少し雰囲気が違ったので、開発を続けていましたが。多分、自分は今、CTCの部長職の中でも一番コードを書いている方なのではないかと思います。
- 里見
- 自ら手を動かしてモノを作ろうとする雰囲気が変わってきたというのは、確かにそうですね。CTCの方針や時代の変化など、様々な要因があるものの、私自身も、自分たちで新しいモノを作っていこうという空気があることは大切だと思っています。その点に関連して、今も自身でプログラミングをされている泉さんはどう感じますか。
- 泉
-
私は、数値解析が主たる業務なので、日々自分でプログラミングをしますが、やはり自身で何かを作っていくという意識は、エンジニアとして大切なものだと感じています。自分の現在の業務に関連して言えば、私は、作業を効率化させるために一部を自動化するためのコードを書いたりしています。私たち科学システム本部は、高い専門性を持つ方が多いので、作業を効率化してそれぞれの専門分野にだけ集中できるような環境を作っていくと、さらに成長できるのかなと感じています。量子の分野についても、理論をしっかり理解して、かつプログラムを書ける人というのがこれからますます重要になっていくと思います。
- 松村
-
私は、ずっとネットワークを担当しており、その分野で専門性を高めてきたのですが、クラウドに移りつつある中、オンプレミスのインフラ案件は少なくなってきています。そのため、自ら新たな分野を学んでいく必要性も感じていて、今年は、先ほど富士榮さんがおっしゃったIDに関わるシステムの研修にも参加しています。一方、既存の知識を次の世代に伝えていくことも大切です。そのためにも現在の専門性は保ったまま、新しいことにチャレンジして色々な人とつながっていくというのが、これから自分がやっていきたいと思っていることです。
- 渡部
-
私はちょうど、先ほど話に出た2000年代初めの入社で、CTC人生の大半をインフラ関連の領域で過ごしてきました。その中で、イノベーション推進室にいた時期は、自分なりにビジネスモデルを考えて、必要なアプリケーションを開発したり、ロボットをプログラミングして動かしたりということをやっていたのですが、そのように様々な業務に携われたことは、自分にとって大きな学びとなりました。その経験から私は、1つの分野だけをずっとやるのではなくて、それぞれの人がもっと色々な経験ができるようになるといいなと思っています。
- 富士榮
-
他方、今のCTCの良さは何かといえば、お客様とやり取りするフロントのエンジニアが皆、一定のビジネスセンスも持ち合わせていることだと思います。つまり、お客様との交渉もできるし、予算や見積もりの算定もできる。それはこの十数年、PMを育ててきたことの成果だと感じています。その人たちがさらに自分自身でプログラムを書き、モノを作ることができるようになって、開発について実感を伴った想像力を持つことができるようになると、CTCはさらに競争力を高められるのではないでしょうか。
- 久保田
-
自分で手を動かして新しいモノを作りたいと思っている人は、CTCには多いはずです。自社で各種開発を進めることの将来性には期待して良いと思います。自分もその点を後押ししていけるようなことを、これから未来研の中でやっていきたいですね。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。