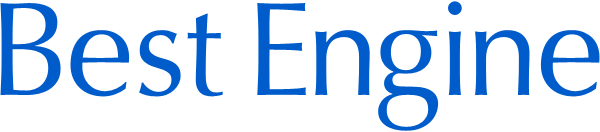今こそ問われる科学の力、人の力

科学技術とITの発展を通して社会が大きく変わろうとしている時代。
本質を理解して物事に取り組む力が求められている。
科学の果たす役割とは何なのか。
長年、科学の現場で活躍してきたCTCの技術者と、科学を広い視野で見つめ続けるサイエンス作家が、科学について、未来について、今もっとも大切なことを紐解きます。
「ブラックボックス」の中身を知る
- 石川
- 伊藤忠テクノソリューションズ(略称CTC)の前身の1つであるCRCソリューションズは、日本でいち早くスーパーコンピュータを導入した会社です。その時代を含めると、当社は既に半世紀以上にわたって科学・工学分野の解析やシミュレーションを行っています。長年、科学と向き合ってきて、現在の「VUCAワールド※1」と呼ばれる激動の時代における科学の役割とは何なのかを、改めて考えたいと思っています。本日は、科学全体を広い視野で見てこられた竹内さんに、この時代の科学のあり方、そしてこれからの世界について色々とお伺いしたいと思っています。
- 竹内
- 私たちはまさに今、社会が大きく変化する節目の時代に生きています。変化の背景には、通信やコンピュータといった科学技術の発展が深く関係していますが、そうした時代においてはとりわけ、科学の重要性が際立ってくると私は考えています。科学とは、そもそも私たちが日々享受している様々な技術の根っこにあるものです。企業が時代の大きな変化の中で生き抜いていくためには、その根っこの部分を持っていることが重要になります。それがないと、例えば人工知能※2社会になったり、量子コンピュータ※3が出てきたり、あるいは地球温暖化で環境が激変するといった大きな変化が起きた時に、変化への対応を可能にする新たなものを、自分たちでゼロから作り上げることができなくなるからです。日本の企業はそこが全般的に弱いので、御社が科学の分野で長い蓄積を持たれていることは今後ますます大きな強みになると思います。
- 石川
- ありがとうございます。私たちは、分野で言えば純粋に「科学」よりも工学や技術に近く、50年強にわたって自社でソフトウェア開発からサービス提供まで行ってきました。構造計算や流体計算、または電磁場の計算においても、外から導入してきた「ブラックボックス」化されたソフトを使うのではなく、自ら開発し、自分たちで手を加えられるソフトウェアを持っています。その意味で、竹内さんのおっしゃる「根っこの部分」を持ち続けてきたと言えるように思います。
- 竹内
- 実はブラックボックスというのは、この時代の1つのキーワードだろうと思います。技術が高度に発展する中、あらゆるものがブラックボックス化してきたのが現代の社会です。それらをブラックボックスのままで扱うのではなく、その中身まで自分で作ろうとするのが科学の精神だと私は考えています。そういう精神を持った上で技術を開発することが、今、企業に求められていると思うのです。
- 石川
- 当社は、特に科学・工学分野において、「独自技術を活かす」ことを重視しています。言い換えると、ブラックボックスそのものを自ら作り上げることとも言えます。例えば建築の構造計算でも、従来は線形領域※4で計算が行われてきました。しかし防災のシミュレーションで言えば、これからは"想定外"と言われるような超巨大地震の検討もしなければならず、非線形領域※4の計算が必須になります。そういった場合、私たちは自らソフトウェアを開発しているため、必要に応じて自分たちでアプリケーションを作り替えること、すなわち新たなブラックボックスを作ることができます。VUCAワールドでは、常に想定外が起こりえます。それゆえまさに今、そのような力の重要性を感じています。
- VUCAワールド
VUCAとは、変化が激しく不確実で、複雑かつ曖昧な状況を意味するアメリカの軍事用語。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の各頭文字による。「VUCAワールド」は、2016年1月の世界経済フォーラム(ダボス会議)で使われたことをきっかけに、今では経営者等の間で頻繁に用いられる語となっている。 - 人工知能
コンピュータを使って、人間の知能を実現させようという技術全般を指す。AI(Artificial Intelligence)とも言う。コンピュータが自ら学習して知能を高めていく「機械学習」を根幹として、これから様々な分野で利用されるようになると見られる。今後10~20年の間に、日本の仕事の約半分が人工知能またはロボットによって代替可能になるともいわれている。 - 量子コンピュータ
量子力学の原理を取り入れたコンピュータのこと。原理的には、現在最速のコンピュータで何万年もかかる計算を数分で終えられるほどの速度を持ちうる。第一号となるものが2011年にカナダのベンチャー企業によって作られ、アメリカの複数の大手企業において既に採用されている。人工知能も、量子コンピュータの利用によってこれから劇的に発展する可能性がある。 - 線形領域と非線形領域
ある現象を数学的に記述した時に、入力値と出力値の関係が足し算と引き算だけで表せる(=1次関数として表わせる)場合、その現象は線形領域にあるといい、それ以外の場合は非線形領域の現象となる。現実に起きている現象はほとんどが非線形領域にあるが、そのままでは複雑すぎて現行のコンピュータでは計算することが難しいため、線形領域で扱えるように単純化してシミュレーションを行うことが一般に行われている。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。