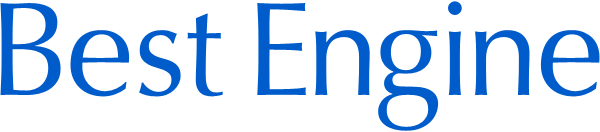|特集|今こそ問われる科学の力、人の力

「自分の仕事で社会を幸せにしていきたい」
- 竹内
- 日本はまさに、企業が引っ張っている社会です。「人工知能社会が来る」といったところで、教育現場はついてこない。けれども企業は率先して進めていますよね。グローバル展開をする企業、IT関連企業、みんな次の手を打っています。日本が今、生き残れている理由は、企業のそういう姿勢のおかげだと思います。その一方で、教育が空洞化しているため、送り込まれる人材のレベルがどんどん低下しているのが現状です。そこが何よりも日本の問題だと僕は感じています。
- 石川
- 視野を広く持ち、自らしっかりと考えられる人材が育ちにくい。グローバルで戦うにしろ、国内で戦うにしろ、科学の分野にしろ、それ以外にしろ、自分の頭で考え、いろんなことを想像できる人材をいかに育てていけるかを企業も学校も、真摯に考えていかなければなりません。そこがしっかりできれば、新しいアイデアも生まれてくる。ブラックボックスをただ使うのではなく、自分でゼロから新しいものを生み出せるようになる。日本には、そうした人材が今、何よりも求められているかもしれません。それが、イノベーションを起こす力にもなると思います。
- 竹内
- もう一つ感じるのは、"真剣に取り組むこと"の大切さです。例えば、防災のプログラムを書いてシミュレーションを実施する時に、本気で人の命を救おうと思えているかどうか。単なる仕事として抽象的なイメージのままでやっていては駄目なんです。自分のこのシミュレーションによって人命が救われるんだという使命感や、自分の仕事で社会を幸せにしていきたいという気持ちが根底にないと、高度な計算技術のようなものがあったとしても、いい仕事はできないのではないかなと思います。
- 石川
- そうですね。私たちは特に、人命や安全に関わる仕事をすることが多いため、その時、科学技術者としての倫理観や使命感というのがとても大切になることを感じます。自分たちが出す結果が社会にどういう影響を与えるのか、どれだけ重要なのか。そこを意識することは決して忘れてはいけないと、常に肝に銘じて取り組んでいます。
- 竹内
- 人間のためのシミュレーションであり、人間のための人工知能でなければいけません。逆になったらだめです。人間が幸せになるには自分たちはどうすればいいのか。技術が発展すればするほど、私たち自身のあり方が問われているのかもしれません。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。