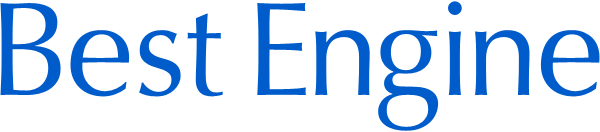|特集|今こそ問われる科学の力、人の力

本質を理解できる力をいかにして育てるか
- 竹内
- 私が子供の頃は、計算尺※5というものがありました。複雑な計算をするために使う定規のようなものです。その使い方に習熟した人が、科学技術計算のできる人でした。私の先生の世代だと、「コンピュータを手で回していた」と聞きます。そこから計算社会が始まってどんどん高度になっていって、今では計算尺と言っても何かわからない時代になってしまった。大学時代、天体力学の大家の先生の授業を受けた時に、我々があまりにもそのような計算技術を知らないので、先生が驚いておられました。私たちが学生だった80年代には既にそういうものが必要ではなくなっていたのですが、自分たちがコンピュータでやっていることを昔の先生は全部頭の中でやっていたと考えると本当にすごいことだと感じました。しかしそんな時代は、今では更に遠い昔になっています。そういう意味で、今の若い人たちは大変さがあるかもしれません。幼少期に既に技術が発達しすぎていて、ほとんどのものがそこにある。ある意味ブラックボックスだらけの中で育っているので、本質を理解するためには、昔以上に努力する必要があるようにも感じます。
- 石川
- そうかもしれません。コンピュータを使うにしても、その中で使われている計算法(=アルゴリズム※6)を知らなければ、なぜこういう結果が得られたのかといった本質は見抜けません。今の風潮として、アルゴリズムをきちんと理解せずにブラックボックスとして使ってしまうことが多く、私もそれを懸念しています。それぞれのアルゴリズムには、これはこういう範囲で有効である、という適用範囲があるわけですが、シミュレーションをする場合、その適用範囲内であれば、ブラックボックスのままでもきちんとした解を出せます。ただ、想定外のことが頻繁に起こりうる世の中ではそれではだめです。想定外に対応するには、アルゴリズムそのものを自分で理解してその範囲を広げるといったことができないといけない。これからの時代、そうした力がますます必要となってくるのに、技術の進歩でどんどん本質が見えにくくなっている。そのあたりが難しいところです。
- 竹内
- 人工知能(AI)が世の中でより広く使われるようになると、もはや一般の人たちにはほとんど理解できないことが今以上に増えていくと思います。また、これまで人間がしてきたような判断もAIが代わりに行うようになれば、私たちは巨大なブラックボックスの中に生きることになるわけで、それには私は反対です。人間のケアレスミスによる事故等を防止するシステムとしてAIが導入されるのはいいのですが、意思決定はAIに委ねたくないというのが私の考えです。ただ、そこすらもAIに任せたほうが安全なはずだと言う人もいると思います。その点は、私たちがどういう社会を望んでいるのか、という問題につながります。AIに任せた結果、大勢の人にとって良くない事態になってしまった時はどうするのか、それは誰の責任なのか等、多くの問題が生まれると思います。私は、最後の責任は人間が負うべきだと思うんです。必ず人間の責任者がいて、最後はその人間が責任を負う。私はこれからもそういう社会であり続けることを望みます。
- 石川
- 私も同じ意見です。最後は人間。だからそれを判断できる人間をいかに育てるかがとても重要なんですよね。
- 竹内
- 何を計算するのか、どこに注目すればいいのか。それを判断するのは、やはり人間の仕事だろうと思います。そういうセンスを、今の若い人たちは学ばなければいけません。ただ問題は、それを教えられる人がいるかどうかです。例えばコンピュータを使いこなすためにはコツがあるのですが、そういうコツを知る先生は少なく、コンピュータの本質やアルゴリズムを理解して教えている先生はほとんどいないかもしれません。既に出来上がっているプログラムを使って数字を入れれば計算してくれる、ということではいけないんです。教育のそのあたりのところをなんとかしていかないと、日本の将来は危ういと思います。
- 計算尺
乗法を加法に変換する対数の原理を用いて、様々な関数計算を可能にしたアナログ計算機。17世紀に英国で発明された。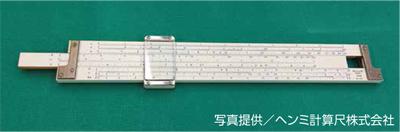
- アルゴリズム
特定の問題を解くための手続きのこと。単純な計算を積み重ねて複雑な問題を解く場合に、アルゴリズムと呼ばれることが多い。最古のアルゴリズムは2つの自然数の最大公約数を求めるユークリッドの互除法と言われている。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。