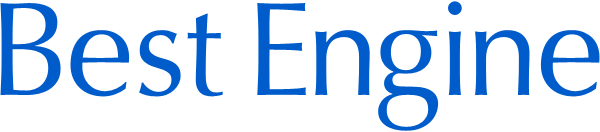|特集|今こそ問われる科学の力、人の力

シミュレーション技術の持つ可能性
- 竹内
-
すべての森羅万象は、計算に置き換えることができます。私たちはシミュレーション技術を高度化させることで、できる限りあらゆるものを計算で表現しようとしてきました。そうして現代の「計算社会」が形成されましたが、今後、量子コンピュータの登場等で計算技術が更に発展し、いずれは「超計算社会」に入っていくと思います。するとあらゆるシミュレーションにおいて、非線形領域までを含めた精緻な計算をするのが普通になる。そうした時代に私たちは差し掛かっています。
- 石川
- シミュレーションの世界で言えば、今後は「大空間の実験場」の時代になるでしょう。つまり、一つひとつの現象を精度よく測定できるだけでなく、現実の世界のような、大空間で相互に関わりを持ちながら起きる複数の現象全体を精密にシミュレーションできるようになるということです。例えば自動車の衝突でも、これまでは現実を単純化して、単に壁に衝突するというようなシミュレーションをするしかなかった。しかし実際に起きることはもっと複雑で、車2台もしくはそれ以上が同時に、しかも横や後ろからぶつかることもありますし、衝突と同時に火災が起きる場合もあるわけです。そのような複雑な現実をシミュレーションで評価することが可能になると思います。

竹内 薫
東京大学で科学史・科学哲学、物理学を修め、その後マギル大学で博士号を取得。科学への深い理解と情熱をもとに、科学評論、エッセイ等を多数執筆。NHK Eテレ「サイエンスZERO」ナビゲーターとしても活躍中。
- 竹内
- 工学や技術は、試行錯誤しながら進むしかないところがあります。どれだけ万全を期して設計して安全点検を繰り返しても、事故は必ず起きてしまいます。大切なのは、そこで事故の原因をしっかりと究明し、問題を取り除くことです。そうすることで改良され、安全性が高まっていく。それが工学の世界です。その時にシミュレーションが果たす役割はとても大きく、その技術が向上していくことは私たちにとって、とても重要だと感じます。2016年12月、新潟県糸魚川市で大火災がありました。約30時間燃え続け、焼失面積は約40,000m2(総務省消防庁発表)にも及びました。例えばあのような火事が起きている最中に、シミュレーションで広がりを予測して、全部が燃えてしまう前に対策が講じられるといったこともできるようになれば、すごく役に立つと思います。
- 石川
- 確かにそうですね。当社は火災についてもシミュレーションで扱っています。現行のコンピュータの速度では、広い範囲で進行している現象について10分後や1時間後にどうなるかを正確に評価するのは難しいですが、今後、量子コンピュータによって計算時間が劇的に短くなれば、そういったことも可能になってくるかもしれません。
記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。